「高い」ホルン~マリア・テレジアその1~(2017/9/18)vol56
この記事の投稿者: HCメンバー
 次回の演奏会で演奏する交響曲第48番ハ長調「マリア・テレジア」のスコアには「2 Corni in C alto」という指定があります(*1)。これは、「2本のホルン(C管アルト)」という意味を表します。
次回の演奏会で演奏する交響曲第48番ハ長調「マリア・テレジア」のスコアには「2 Corni in C alto」という指定があります(*1)。これは、「2本のホルン(C管アルト)」という意味を表します。
ではまず「C管」。ハイドンの時代、金管楽器はまだ自然倍音のみのいわゆる無弁楽器であり、曲の調性によって奏者は楽器を持ち替える(または管を差し替える)必要がありました(ハ調の場合はC管の楽器というように)。
次に「アルト」。イタリア語で「アルト」は「高い」、「バッソ」は「低い」の意味です(*2)。
ハイドンの時代、ホルンのC管およびB管には、それぞれ「高い/低い」の二種類の楽器(同じ音符を吹いてもオクターヴの差がある)が存在していました(*3)。従って、ここでの指定は「高いC管」のホルン、ということになります。
そして、この「高いC管」が指定されている(超高域パッセージが頻発する)故に、「マリア・テレジア」という曲は、ホルン奏者にとって おそらく最も難易度の高い曲の一つになっていると思われます(*4)。ホルンの高音域が出てくる曲として有名な、ベートーヴェン:交響曲第7番/第1・4楽章やモーツァルト:交響曲第29番/終楽章の最高音が実音Eであるのに対し、この曲では冒頭のファンファーレ始め、メヌエット、終楽章ではその上のGまで、さらに第一楽章最後ではAまで出てきます。
それらの音をちゃんと出すのはいかに大変なことであるか、ということをきちんと(イメージとして)理解した上で、周りの人間としては静かに声援を送りたいと思っています。(ホルン好きなファゴット吹き)
*****
*1)alto/basso を作曲家が明示しない時もあるので問題になるのですが、この曲の場合、1769年の日付を持つヨゼフ・エルスラーによる筆写譜には、はっきりaltoと書かれているそうです。
*2)声楽における「アルト」の成り立ちが、テノールとソプラノを響きの上で補うために、テノール声部の上(高い)に対置する声部として「アルト」が置かれた という経緯によります(下に置かれたのが「バッソ」)。
*3)「アルト」管および「バッソ」管の二種類の楽器が存在するのは、原則としてこの二つの調(B/変ロ調、C/ハ調)の場合に限られます(ただし大まかに言って、B管の場合はアルト、C管の場合はバッソが多い)。A管バッソやD管アルトというのは原則ありません(一部の例外として、モーツァルト:交響曲第19番変ホ長調K132にEs管アルトという指定あり)。
*4)以下のような記述がある「マリア・テレジア」の曲目解説もあります。
the work requires precise strings, excellent wind and especially risk-taking Hornist
トラックバックURL:
https://haydn.jp/2017/09/18vol56/trackback/





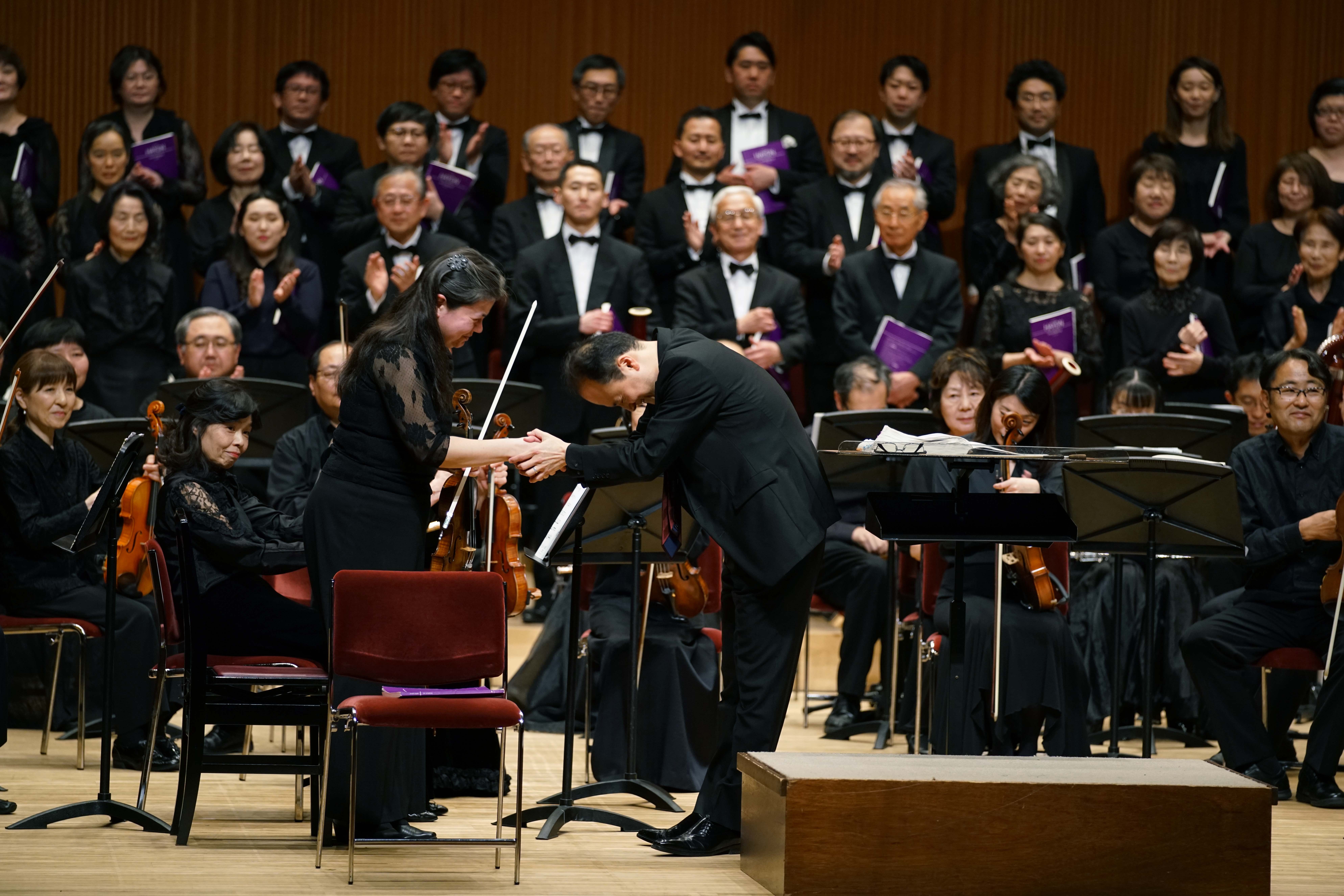








コメントを残す